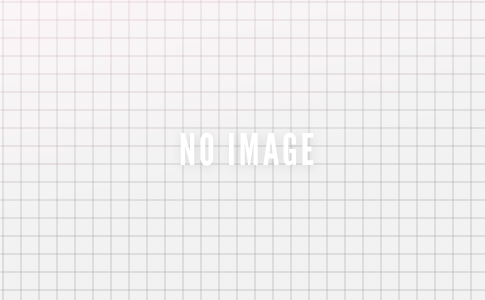「所属する選手全員が成長する」
入会案内に書いている一文であり、クラブ理念の根幹です
少し掘り下げて話していきます
競争力
「人数が多いクラブは競争があるから強くなる」
これは正しい部分もあるけど、正しくない部分もある
例えば中学生(11人制)で、1学年に30名所属しているとする
その30名の能力.意識.意欲が同等なレベルで競い合っている場合は競争力が上がる
でも30名もいれば差はあるだろうし、特に意識.意欲に差があると広がっていく一方だろう
Aチーム、Bチーム、Cチームと分けて「上に上がるように頑張れ」としても
Cチームでスタートした選手がAチームを目指してモチベーション高く3年間頑張り続ける
それを継続してやり続ける選手がどれだけいるのだろうか
そして選手の人数が増えれば指導者の人数も増やさなければならない
それもCチームの選手がAチームに上がれるほど成長させられる指導力を持った指導者が
現実的には非常に難しいことだ
だから人数が競争力を上げる要因の一つではあるけど、必ずしもそうではないと思っている
全員を出す
「人数が多くないから出れるのが当たり前になる」
これも競争力が上がらない理由と言われるんだけど
そもそも論だけど、人数が少ないから全員出れるんじゃなくて
『VIVOでは人数が多くても全員を試合に出す』
そういう理念を持ってやっている
もちろん公式戦などは全員を平等には出れません
最終的にチームの目標は試合に勝つこと
だから大会ではその時点でのベストメンバーで挑む
でも、その大会へ向けての期間は全員に同様の経験値を積ませている
それは練習の時も同じで、全員が平等に成長のチャンスを得られるよう意識している
6年生であれば、6月の学童五輪に向けてチーム作りをして終わったらリセット
そこから再スタートして11月の全日本少年まで切磋琢磨してきた
それは他のカテゴリーも同じである
結果と育成
チームの結果を求めるのか、個人の育成を目指すのか
どちらを優先するのか、みたいな話は昔からよく聞く
けど、結果と育成は両立すると考えている
サッカーはミスが起きるスポーツであり、ミスから得点が生まれるものである
だからチーム内で上手い選手にボールを集めて、下手な子にボールを持たせない
これが簡単にミスの可能性を減らして、内容も結果も安定させやすい手法だと思う
ある程度のレベルまではね
相手のレベルが本当に上がれば、1人2人の上手い選手がいたとしても厳しくなる
それこそ九州大会までは出たことがあるが、一言で言えば全員上手い
だからこそ、全員が上手くなって欲しい
それにチームメイトが普段の練習相手だから、みんなが成長しないとチームはレベルアップしない
だから個人の育成があってこそのチームの結果である
嬉しい瞬間
サッカーを始める時期もそれぞれで、最初の運動能力も人それぞれ
初期能力が低くてもコツコツやっていくと芽が出だす
例を挙げると〇年生の〇イト
数年前入ったときは思ったとおりにいかないと泣いたり練習から外れることもあった
そんな彼が今ではランをすれば学年トップで帰ってくる
リフティングもずっと一桁だったのが50回は超えたのかな
1対1とかでも上の方へ勝ち上がってくるし
試合でもいいプレーが増えてきて、みんなから「ナイス」と言われることが増えてきた
こういった成長していく姿を見られるのが一番嬉しい